片山工房は、神戸市長田区にある「障害のある人たちのアートを軸に活動する福祉施設」です。ところが、片山工房では全員がアート活動をしているわけではありません。お茶を飲んで過ごすだけの人、スタッフと話すだけの人もいます。シンプルに言い換えれば「本人がしたいことをする場」。あるいは、一人ひとりのメンバーが、自分のやりたいことを探ることのできる、「自由と安全が保証された場」とも言えるかもしれません。片山工房が、「本人のやりたいこと」にフォーカスし続けるのはどうしてなのでしょう? 理事長の新川修平さんとスタッフの川本尚美さんにお話を伺いました。

絵の具を蹴ったら“明日”が見えた!
キャンバスの左上から右下に向かって、ブワアっと広がる黒い色に、スピード感のある赤い色が走り重なっている絵。まるで、一瞬のできごとが閉じ込められているようです。勢いに飲まれてじっと見ていると、「澤田隆司さんが、ペンキを入れたコップを足で蹴って制作した絵です」と新川さんが教えてくれました。実は、澤田さんの「蹴る」という制作方法は、片山工房のはじまりに深く関わっています。片山工房の前身は、1993年に設立された自立生活センター。障害のある人が軽作業などの仕事をする作業所でした。ところが2003年4月、支援費制度の導入をきっかけに作業所の閉鎖が決まります。介助スタッフとして勤務していた新川さんは「利用者の行き場がなくなってしまう」と代表を引き継ぐことにしました。
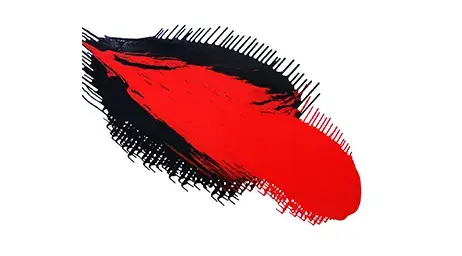
「代表になってすぐに軽作業をやめてみたんです。そしたら“人”が見えた。めっちゃ面白い人ばかりだし、一緒に何かできるんじゃないかと思ったんです」。新川さんは、初めて一人ひとりに「何かしたいことはありますか?」と問いかけました。すると、それぞれの「したいこと」が返ってきました。たとえば、澤田さんは「字を書くこと」。体のなかで唯一動く右足で挑戦しましたが、字は書けませんでした。ところが、足首のスナップが強いことがわかりました。「このスナップを使って、何か面白いことはできないだろうか?」ある時、新川さんは紙コップに赤い絵の具を入れて、傾斜をつけた画用紙に向かって蹴ってもらうことを思いつきました。「ぶわーっと画用紙が赤に染まるのを見て、僕は初めて『明日何しましょう?』って言えたんです。明日が見えたんですね、その行為に。これは長続きするかもと思いました」。赤く染まっていく画用紙と一緒に、新川さんのモノクロだった世界がカラーに変わったのです。

動く=働く
片山工房は、2011年にその名の由来となった「片山町」から現在の「川西通」に移転。アート(表現)活動を主軸とする生活介護事業を始めました。他の施設と併用して「週1日だけの通所も可」としたのは、「メンバーが自由に行きたい場所を選べるように」という配慮からです。片山工房では、メンバー全員が絵を描くわけではありません。「絵を描く場を探すなかで片山工房を見つける方もいれば、家から出てすごす居場所として選ばれる方もいます」とスタッフの川本尚美さんは話します。新しいメンバーが来るたび、スタッフはその人に向き合いながら、時間をかけて「本人がやりたいこと」探していきます。その結果として、「絵は描かずに、スタッフと話すだけ」という人もいてよいと考えています。

「メンバーとの間で、僕が一番大事にしているお約束はここのシャッターを開け続けること」と新川さん。この場にいる「メンバーから生まれてくるもの」をシンプルに大切にしています。たとえば、メンバーが「片山工房に通う」こともそのひとつ。実は、片山工房ではあえて「送迎」を行なっていません。なぜなら、メンバーが公共交通機関を使うことによって「住みやすさ」を生む可能性があると考えているからです。「ドアツードアの送迎をすると、障害のある人の姿が見えなくなってしまう。うちのメンバーと電車や駅からの道で出会ってもらい、『いろんな人がいる』と感じてもらうことも大事だと思うんです。」と新川さん。実際に、メンバーが使用する駅に仮設エレベータが設置されて、車椅子やベビーカーを使いやすくなったという事例もあるそうです。

「働く」の定義は「お金を稼ぐ」ことだけではないと新川さんは考えています。「『働』という漢字は『人が動く』と書きますよね。メンバーが『動く』ことによって環境を変えることも、『働く』ことになる。どんどん社会を耕してもらっていると思っています」。
失うことは満ちること
片山工房には、「障害のある人と社会とのつながり方は一次的なほうが良い」という信念があります。作品を二次利用した商品化は行わず、「作品を発表するなら原画で」と決めています。2018年には、滋賀・やまなみ工房との合同展や神戸市民ギャラリーでの片山工房15周年記念作品展などを実施。なかでも、一般社団法人Get in touchの協力の下に行われた、スターバックス三宮磯上通店と阪神甲子園駅前店での常設展示は、これまでにない取り組みとなりました。「阪神甲子園駅前店から『トラを描いてほしい』という依頼があったときは悩みました」と新川さん。依頼で絵を描くとなると、片山工房が大切にする「本人のやりたいことをやる」ことから外れてしまうからです。「本来の僕の考え方からは全くのタブーだった」と振り返ります。

しかし、Get in touchの担当者との信頼関係のなかで、「依頼に対して描くという関係をつくる」というチャレンジを決断。スターバックス両店舗での展示は、「Instagram」上にたくさんの画像がアップされるなど大きな反響を呼びました。「今回の試みの是非については明確な答えはない」と新川さんは考えています。言葉でやりとりがしにくい、知的障害の人の意思を確かめるのはとても難しい。しかし一方で、「エッジの効いた作品が描かれているという事実」に対して、世に出していく流れをつくる必要も感じています。だからこそ、世の中に作品を出すときもまた、「それがどういう意味を持つのか」を親御さん含めてじっくり話し合います。どんなときも、原点にあるのは「人が軸」であること。「目の前のこの人と何をするか」を考え抜いてアクションするからこそ、片山工房は唯一無二のインパクトを持つ場になり得ているのだと思います。
〈まなび〉とにかく徹底的に目の前の人と向き合うこと!
するとやるべきことが見えてくる。
片山工房
障害のある方々に、アート(表現)が、自己の持っている能力を最大限に活用できる手法と捉え取り組んでいます。社会のスピードについてゆく事だけを、目的とした団体ではなく、持って生まれた個性に着目することで、自己決定がしやすい場、「やれば何かが産まれる」ことで「明日が見える」を提供することが、社会とつなぐ場として必要と考え、常に「人」が軸を第一義に考えた工房です。
WEBSITEを見る













